米Googleは5月20日(米国時間)、オープンソースのモバイル向けOS環境「Android 2.2」を発表した。開発者向けに「Android 2.2 SDK」および「Android NDK, Revision 4」も公開されている。
Ubuntu 10.04 LTSガイド(後編):SNS連携機能や音楽配信ストアを使う
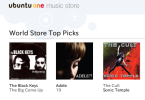
Ubuntu 10.04 LTSで注目すべき新機能として、TwitterやFacebookといったSNSとの連携強化や、音楽配信サービス「Ubuntu One Music Store」のサポートなどが挙げられる。Ubuntu 10.04 LTSレビュー後編では、これらの新機能を紹介する。
Linuxカーネル 2.6.34リリース、新ファイルシステム対応や電源管理機構の強化など改善点多数
Linus Torvalds氏は5月16日、Linuxカーネル 2.6.34のリリースを発表した。2月末の2.6.33公開以来、約3か月ぶりのリリースとなる。「特に興味深いものはない」とTorvalds氏は記しているが、新たに2種類のファイルシステムに対応するなど、多数の機能強化が図られている。
RHEL 5.5互換のLinuxディストリビューション、CentOS 5.5リリース
CentOS開発者は5月14日、Red Hat Enterprise Linux(RHEL)互換のLinuxディストリビューション「CentOS 5.5」をリリースしたことを発表した。対応アーキテクチャはi386およびx86_64で、RHEL 5.5をベースとしている。
Google日本語入力、「Mozc」という名称でオープンソース化
グーグルは5月11日、同社のリリースする日本語変換ソフト「Google日本語入力」を「Mozc(モズク)」という名称でオープンソース化したと発表した。同社の開発するLinuxベースOS「Chrome OS」の開発版である「Chromium OS」への対応を目的としたもの。
PS3でのLinux機能削除に対し米国で集団訴訟が起こされる
ソニーが「Play Station 3(PS3)」でLinuxなど「その他のOS」インストール機能を無効化したことについて、米国のユーザーがSony Computer Entertainment Americaを相手取り集団訴訟を起こした。「貴重な機能を意図的に無効化した」と述べている。
ストレージやネットワーク、アプリケーションなどを異なる仮想マシン上で実行することで堅牢製を高めた「Qubes OS」公開
ポーランドInvisible Things Labは4月7日、「仮想化技術を利用した強固なセキュリティ」をうたうデスクトップ向けOS「Qubes OS」アルファ版を公開した。Xenハイパーバイザ上で複数のOS環境を同時稼働させ、ストレージやネットワーク、アプリケーションなどを異なる仮想マシン上で実行させることでセキュリティを強化する。年内の正式版公開を目指している。
xorg-server 1.8.0が登場、udevによる入力デバイスの自動設定がデフォルトに
X.Org Foundationの開発者は4月2日、X Window Systemのオープンソース実装である「X.org X server(xorg-server) 1.8.0」をリリースした。X11 Licenseの下、freedesktop.orgのgitリポジトリなどから入手できる。
リコーがLinux Foundationに加入、同社のLinuxへのコミットメントをアピール
Linuxを推進する非営利団体のLinux Foundationとリコーは4月5日(米国時間)、リコーがLinux Foundationに参加することを正式発表した。リコーは今後、Linux Foundationのイベントと作業部会OpenPrintingに参画する予定だ。
MeeGoがいよいよ始動、開発者向けリリース公開——「N900」とAtom搭載ネットブックに対応
Linux FoundationのMeeGoプロジェクトは3月31日、初のシステムイメージを公開した。ARMベースの「Nokia N900」、「Intel Atom」ベースのネットブックと「Atom Moorestown」ベースのモバイル端末に対応、プロジェクトのWebサイトよりイメージをダウンロードできる。
レッドハット、Red Hat Enterprise Linux 5.5を提供開始
レッドハットは3月31日、企業向けのLinuxベースOS最新版「Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 5.5」を提供開始すると発表した。比較的小規模な機能強化やセキュリティ修正、バグフィックスなどが行われたマイナーアップデートとなる。仮想化やクラウド・コンピューティング関連機能を強化、Windowsとの相互運用性も向上されている。
LPI-Japan、東証新システム「arrowhead」の技術セミナー開催
LPI-Japanは、東証のLinuxベース新システム「arrowhead」(アローヘッド)をテーマにした技術セミナー「世界最高水準! 東証 新ITシステム技術セミナー」を2010年4月28日、ベルサール九段3F(東京都千代田区)開催する。有料で参加費は8400円。Webサイトから申し込み受付中。定員200人。
Linux Foundation、2010年度の「Linux.com Linux Guru」を発表
Linuxを支援する非営利団体のLinux Foundationは3月22日(米国時間)、「2010 Linux.com Linux Gurus」として、同団体がLinux.comで展開するコミュニティ活動への参加や貢献が高いと評価された人5名を発表した。
ユビキタス、Android端末を2秒未満で起動できる「Ubiquitous QuickBoot」
ユビキタスは2010年3月23日、さまざまな組み込み機器の瞬間起動を可能にしするソリューション「Ubiquitous QuickBoot Release1.0」を発売した。Androidによる実装例では、電源投入からアプリケーション実行状態までの復元を世界最速の1秒台で実現したという。
最新テーマを取り入れた「Ubuntu 10.04 LTS」ベータ1が登場
英Canonicalは3月19日、次期Linuxディストリビューション「Ubuntu 10.04 LTS」(開発コード「Lucid Lynx」)のベータ1を公開した。最新のテーマ「Light」を搭載、ロゴも一新した。
リモートデバッガ/プロファイラを利用したデバッグ&性能解析

ネットブックやMIDといったリソースの少ないマシンで動作するアプリケーションをデバッグする場合、実行環境とは異なるマシンでアプリケーションの動作状況をモニタリングするリモートデバッグが有用だ。本記事ではGDBや「インテル アプリケーション・デバッガー」でリモートデバッグを行う基本的な手順を紹介するとともに、「インテル VTune パフォーマンス・アナライザー」を用いたパフォーマンス解析についても紹介する。
Moblinアプリケーションのクロスコンパイルとインテル コンパイラーによるパフォーマンス改善

Moblinアプリケーションはクロスコンパイル環境での開発が推奨されており、通常のLinux向けアプリケーションとは若干開発手順が異なる。本記事ではIDEを使った基本的な開発手順や、インテル コンパイラーを利用してMoblinアプリケーションをコンパイルするための設定方法を解説する。また、インテル コンパイラーとGCCの性能比較結果についても紹介する。
The Linux Foundation、モバイル向けLinuxベースOS「MeeGo」のセミナーを4月21日開催
The Linux Foundation(LF)は、モバイル機器に最適化したLinuxベースOS「MeeGo(ミーゴ)」の普及を目指すセミナー「MeeGo Seminar Spring 2010」を2010年4月21日開催する。MeeGoは、インテルの「Moblin」とノキアの「Maemo」を統合したモバイル向けプラットフォームで、LFが「MeeGoプロジェクト」として運営する。
「Fork You」ロゴ入りグッズなどギーク向け商品を揃える「Linux.com Store」オープン
非営利団体Linux Foundationは3月10日(米国時間)、コミュニティサイトLinux.com内に「Linux.com Store」を開設した。Tシャツ、マグカップ、ステッカーなどのアイテムを購入できる。
Androidを組み込み向けに拡張したOS「Embedded Master」一般公開
Open Embedded Software Foundation(OESF)は2010年3月10日、Androidを拡張した組み込みシステム向けOS「Embedded Master」を一般公開した。Androidのフレームワークを継承し、APIの互換性を保ちながら組み込みシステムに必要な各種の機能を搭載した。ソースコードは、プロジェクト共有・公開サイト「GitHub」からダウンロードできる。